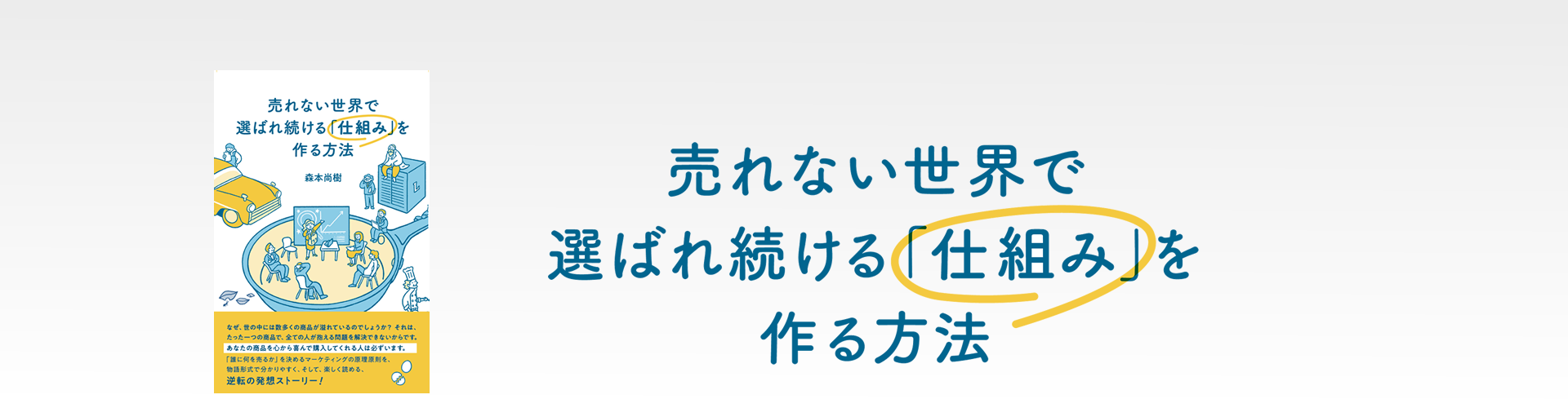
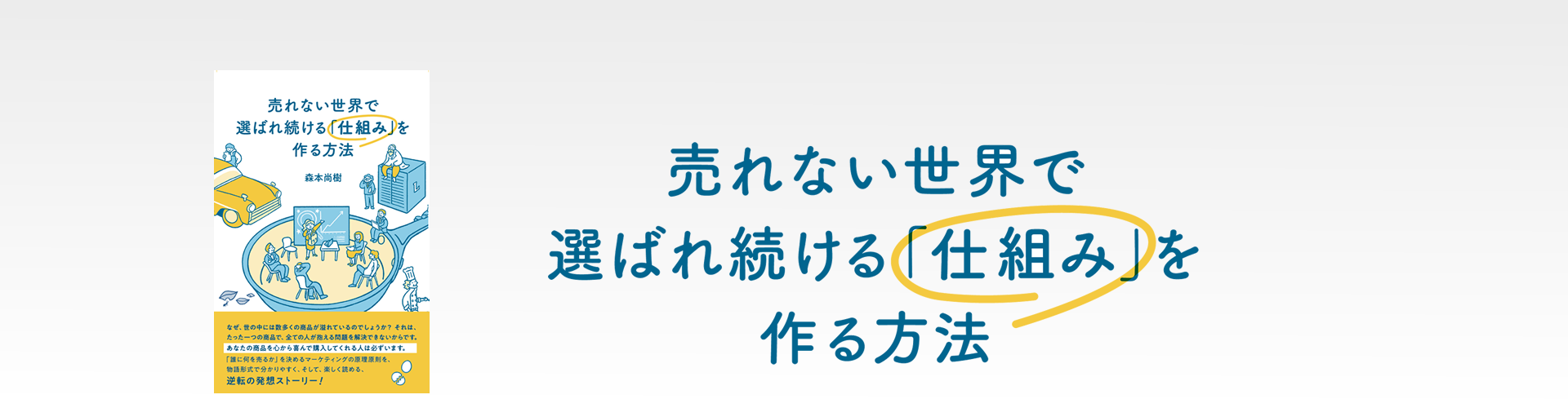
第1章
1
「石崎先生、ご無沙汰しております」
片山勇は応接室に入ると、弁護士の石崎良夫に笑顔で歩み寄り、力強く右手を差し出した。
「片山社長、お元気そうで」石崎がその手を堅く握る。
石崎とは六か月ぶりの再会だ。石崎は七十五歳。四十五歳の片山とは、ちょうど親子ほどの年齢差がある。
「レノン・コンサルティングから報告を受けています。本当によく頑張られました」石崎がこぼれそうな笑顔で片山の右肩に左手を添える。
「先生には感謝しかありません」
父親の急逝で、片山鋳造の三代目として代表取締役に就任したのが一年半前。その時点ですでに会社は倒産寸前の状態だった。
片山鋳造は創業六十年。大手自動車メーカーや装置メーカーの協力会社として、アルミニウム部品の鋳造を行う、従業員数三八〇名の中堅企業だ。精密部品の鋳造に関する技術力は高く、創業以来、安定した経営を続けてきたが、近年ではその業績に翳りが見え始めていた。
そうした中、三年前の主要取引先の経営破綻をきっかけに、経営は急速に悪化。片山が代表取締役に就任してから、わずか半年で万策尽きていた。
その危機を救ったのが、レノン・コンサルティングだった。
「あの時、石崎先生からレノン・コンサルティングのご紹介がなかったらと思うと、今でも生きた心地がしません。すべては石崎先生とレノン・コンサルティングのおかげです」
「ウィリアム・レノン教授は、魔法の杖はない、と口癖のように言っていたそうです。レノン・コンサルティングが、魔法をかけて片山鋳造の業績を回復させたのではありません。すべては片山社長と従業員のみなさまのお力です」
「ありがとうございます。しかし、まだまだたくさんの壁があります」
「今の片山鋳造なら、絶対に乗り越えられます」
石崎と出会ったのは十年前。片山がまだ医療機器メーカーに勤務していた頃だった。泥沼化する可能性があった米国企業との特許係争を収拾してくれたのが、石崎が日本法人の代表を務めるスタンスフィールド国際法律事務所だった。
一年前、片山鋳造の特別精算を視野に入れざるを得なくなった時、片山がまっさきに思い出したのは石崎だった。石崎は現状を精査した上で、レノン・コンサルティングの指導を受けてみることを勧めた。石崎への信頼がなければ、片山は正体不明のコンサルティング会社から指導を受けようとは思わなかっただろう。
「レノン・コンサルティングとの契約も、あと二か月ですね。その後、レノン・コンサルティングからはどのような助言を受けているのですか?」
「今はマーケティング・セクションの創設を提案されています」
「それは……よいことをお伺いしました」
「と、申しますと?」
「実は、クライアントから、マーケティング・セクションでインターンを受け入れてくれる会社を紹介してほしいとの依頼がございまして……。マーケティング・セクション創設の折には、片山鋳造で受け入れていただけませんか?」
「石崎先生からのご相談なら。でも、片山鋳造でいいんですか?」
「もちろんです。ぜひ、よろしくお願いいたします」
片山が笑顔で大きく頷くと、石崎は安堵の表情を浮かべ、コーヒーを美味しそうに飲んだ。