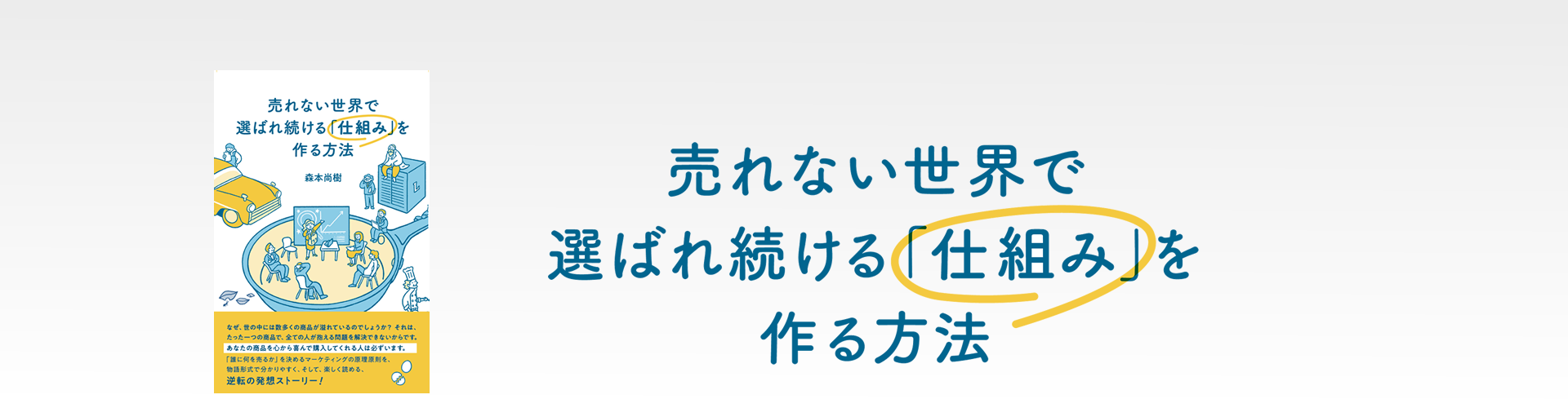
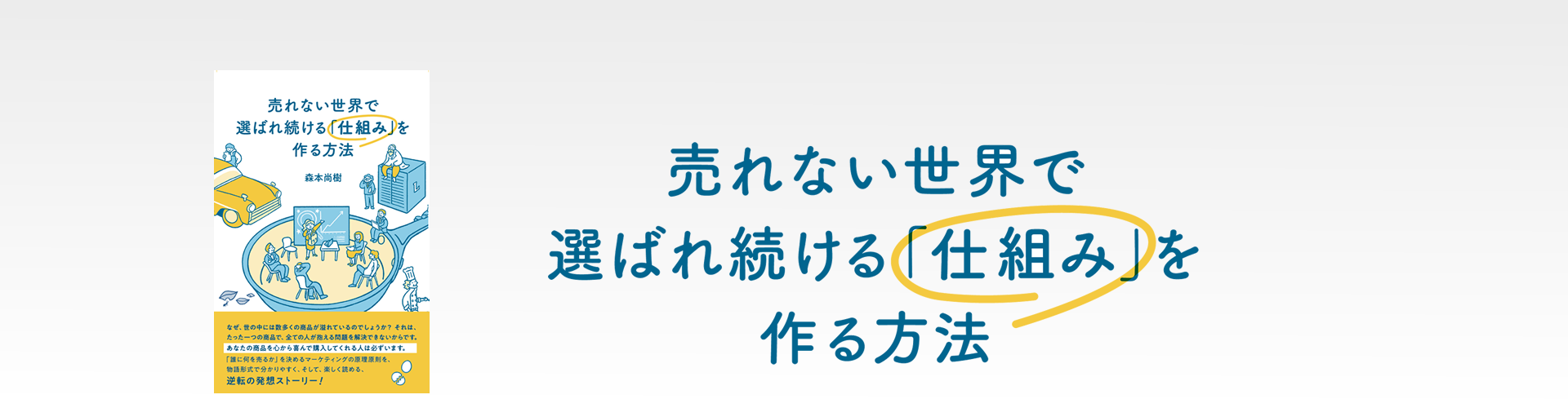
3
マーケティング室の室長に就任して二週間が経った。
突然立ち上がらなくなったノートパソコンを総務部に返却し、岡田は代替機を受け取ったその足で本社管理棟の第一会議室へと急いだ。本社管理棟は、昭和初期の小学校のようにも見える、老朽化した木造平屋建てだ。
会議室の扉をノックする。古びた木製の扉だ。中から返事は聞こえてこない。もう一度、小さくコンコンと叩いてから、そっと扉を開いてみた。
広い会議室の奥に、ダークブルーのビジネス・スーツを着て、長い髪を後ろで一本に束ねた、小柄な女性が座っている。膝の上に、ビジネス・スーツには少し似つかわしくない麻の白い大きなショルダーバッグを大事そうに抱えていた。扉が開いたことには、まだ気づいていないようだ。
「こんにちは」と声をかけてみた。彼女はビクンと体を反応させた。あわてて立ち上がると、ショルダーバッグを抱えたまま、正面に向かいペコンと頭を下げた。自分が挨拶したのが壁だと気づいたのか、今度は体を岡田に向け、頭を下げ直した。
「はじめまして。マーケティング室の岡田です」
「は、はじめまして。小橋遥です」
彼女の名前は小橋遥。二十一歳。片山鋳造が新たな取り組みとしてスタートしたインターンシップ制度にさっそく応募してきたのだ。彼女はマーケティングを学んでいるらしく、本人の希望もあり、マーケティング室で二か月間受け入れることになった。
「改めまして、マーケティング室の室長、岡田です。よろしくお願いします」
遥は名刺を大切そうに両手で受け取ると、深呼吸をして、自分の胸のあたりを小さくポンポンポンと叩いてから早口で喋り始めた。
「小橋遥です。マーケティングを学んでおります。机上でしか知らないマーケティング理論が、現場でどのように活かされているのを知りたくて、インターンシップに応募いたしました。ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、ご指導のほど、よろしくお願いいたします」
「あの、ちょっとガッカリさせてしまうかもしれませんが、実はマーケティング室は二週間前に創設されたばかりで、マーケティングのことが分かる人はいません。まだみんなでマーケティングの勉強会をしているような状況で……。小橋さんの勉強にはあまりならないかもしれません」
遥は大きくかぶりを振る。
「なので、小橋さんが学ばれているマーケティング理論も、僕らの勉強会で共有してくれるとうれしいです」
「私が学んできたことなんかでよければ、喜んで!」遥は目を輝かせながら、大きな声でこたえた。