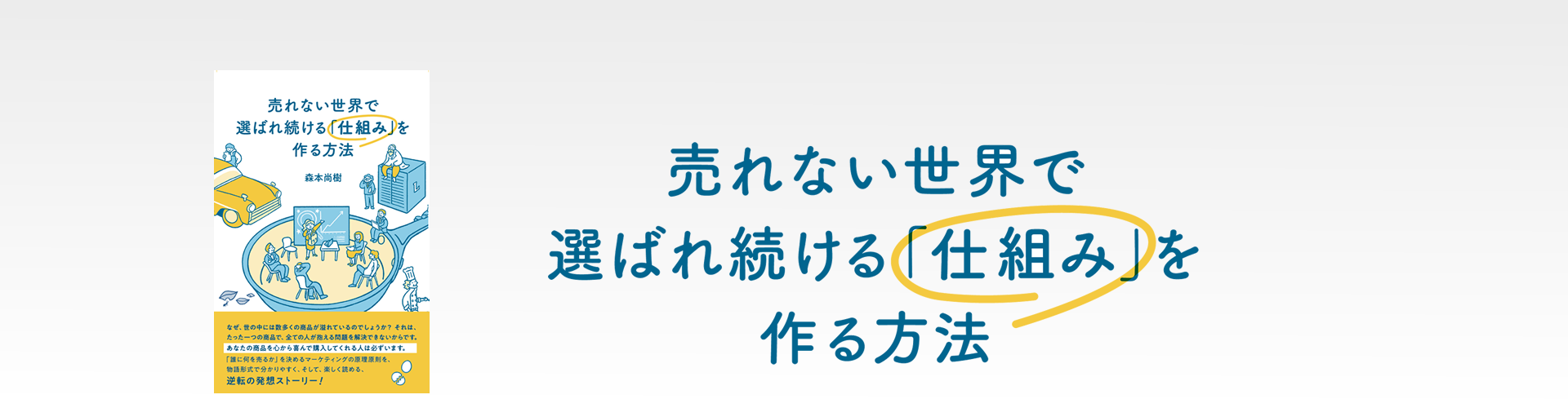
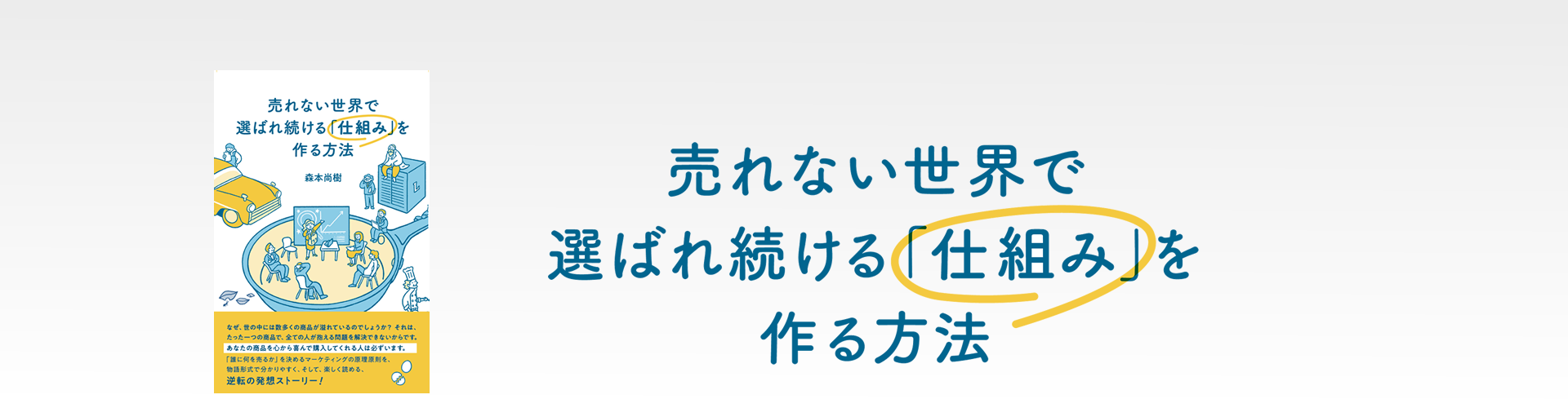
4
遥はショルダーバッグを肩から斜めにかけ、岡田を追いかけるようにして歩く。歩くたびにバッグが大きく左右に揺れる。
マーケティング室は、本社管理棟の中にある。二十年前に第二工場と新管理棟が完成し、製造部門、設計部門、営業部門が移転してから、本社管理棟には社長室と管理部門と、いくつかの会議室があるのみで、それ以外はすべて空部屋となり、物品倉庫と化していた。
マーケティング室に与えられた部屋は、北東側の隅にあり、二週間前までは不用品置場として使われていた。もともとは会議室だったらしく、壁面には大きな黒板も備え付けられている。部屋の片隅にはまだ、不用品が詰め込まれた段ボールが積んである。この段ボールの中のひとつには、片山鋳造が法人化した五十年前に作られた、『片山鋳造株式会社』の刺繍が入ったえんじ色の作業服が、新品のまま大切に保管されていた。片山鋳造が躍進を始めたまさにその頃に、誰もがプライドを持って着ていた伝説の作業着だ。捨ててしまうには忍びなかったのだろう。他の段ボール箱の中には、生産が中止された部品の木型や、紙で管理されていた時代の図面なども保管されていた。
●
マーケティング室の扉を開けると、佐野源次郎、鮎川かおる、奥山和希の三人が笑顔で立っていた。ここに岡田を加えた四人がマーケティング室の全メンバーだ。遥はこわばった顔で部屋に入った。
「みなさん、インターンの小橋遥さんです。これから二か月間、我らマーケティング室の五人目の仲間です!」
四人が大きな拍手を贈る。遥は目を丸くしながら頭を下げた。
「ここが小橋さんの席です!」鮎川が手を広げる。
遥は鮎川に小さく会釈をした後、目を輝かせて自分の席に近づくと、うれしそうに椅子の上にショルダーバッグを置いた。
「じゃあさっそくだけど、源さんから自己紹介をお願いします。好きで好きでしょうがないことも教えてください!」
「佐野源次郎です。みんなからは源さんと呼ばれています。あと、好きで好きでしょうがないことは、孫のしーちゃんと遊ぶことです。しーちゃんは、いつも、『じーじだいすき』と言ってくれます。そんなこと言ってくれるのは、今やしーちゃんだけです。こんな老人ですが仲よくしてやってください」
メンバーは笑いながら拍手をした。遥も緊張した顔のまま拍手をした。好きで好きでしょうがないことを聞けば、その人の、人となりを知ることができる。
「源さんは腕利きの鋳造職人で、創業期から片山鋳造のモノづくりを支えてくれたレジェンドです。定年退職後も、嘱託で若い職人たちにその技術を伝承してくれています」
源次郎は七十五歳。いつも笑顔を絶やさない源次郎だが、現役時代は、とても厳しい職人だったらしく、役員たちは今も源次郎のことを畏れている。
「奥山和希です。好きで好きでしょうがないことはゲームです。貯金も、冬のボーナスも、全部ゲーミングパソコンに消えました。ゲームの中ではウィザードと呼ばれて尊敬されていますが、営業部ではお荷物くんと呼ばれていました。よろしくお願いします」
「奥山くんは機械メーカーを担当する、第二営業部の最若手の腕利き営業マンでした。お荷物なんてとんでもない。奥山くんの強みは何と言ってもゲームで培ったその戦闘力。どんなに難しい営業先でも、果敢に攻略します」
メンバーが拍手すると奥山はおどけて拳を突き上げた。メンバーの笑い声につられて、遥も笑った。二十六歳。最年少の奥山はマーケティング室のムードメーカーだ。
「鮎川かおるです。私が好きで好きでしょうがないことは写真を撮ることです。人物も、自然も、動物も、乗り物も、何でも撮ります。これからどうぞよろしくお願いします」
鮎川は優しい笑顔で、遥に向かって丁寧にお辞儀をした。遥も同じようにお辞儀を返す。
「鮎川さんは片山鋳造の最盛期を支えてくれた伝説のCADオペレーターです」鮎川は四十二歳。男社会の片山鋳造の中で、いつも凛としていて優しさを感じさせる女性である。
「では最後に僕。改めまして岡田祐二です。以前は自動車メーカーを担当する第一営業部に所属していました。好きで好きでしょうがないことは、フットサルやソロキャンプと、今まではたくさんありましたが……今は何と言ってもマーケティングです。そして、マーケティング室のメンバーのことが本当に好きで好きでしかたありません!」
「何それ!うまいなー!」
奥山が岡田を指差し、みんなが笑った。遥も楽しそうに笑っていた。
●
四週間前に発表されたマーケティング室創設の社内通達は、多くの社員たちを驚かせた。特に社内をざわつかせたのは、二十九歳の岡田の部門長への抜擢だった。創業以来、頑なに年功序列の人事を重んじてきた片山鋳造では、岡田のような若手が部門長に選ばれたことは一度もなかった。
室長の人事が発表された後に、続けてマーケティング室メンバーの社内公募が行われた。片山に対する反発や、マーケティング室の創設、抜擢人事の経緯に対しての疑問や批判の声がくすぶる中、応募してくれる人はなかなか現れなかった。結局、公募が締め切られる日に自ら手を挙げてくれたのが、この三人のメンバーだった。
多くの人は、特販チームの失敗は岡田の責任だと信じていた。岡田が一切言い訳をしない一方で、吉川が岡田の不満をあちこちで漏らしていたせいもある。
源次郎はたしかに腕利きの職人だ。その技術、知識、勘は今も健在だ。しかし、コンピュータで制御する現在の製造方法では、その出番はない。古典的な鋳造技術を知り尽くす源次郎の指導を、若手の職人たちは楽しみにしていた。一方で、鋳造のさらなる効率化をめざしていた製造部の管理職者たちは、源次郎の指導を必ずしも快くは思っていなかった。
奥山は二年前に自ら開拓した、大型受注でミスを犯した。結果として会社に大きな損害を与えてしまった。同時期に主要取引先の経営破綻が重なり、まるでそれも奥山のせいのような言われ方をした。第二営業部でお荷物と呼ばれていたことがあるのは事実らしい。
もの静かで優しい鮎川だが、正義感が強く、誰に対しても間違っていることは間違っていると物申してきた。そんな鮎川はやがて煙たがられ、数年前からは、設計の仕事から外され、過去の膨大な設計図や木型の管理を行う、業務管理の仕事に回されていた。
マーケティング室に集まったメンバーは、それぞれが何かを抱えていた。だが、それは仕事と真剣に向かい合ってきたがゆえだ。そんなメンバーを岡田は心から尊敬していた。
「では、小橋さんの好きで好きでしょうがないことも教えてください!」奥山が言った。
遥は小さく頷き、また自分の胸のあたりを小さくポンポンポンと叩いてから、早口で話し始めた。
「私の好きで好きでしょうがないことは、アリの観察です。アリは集団でコロニーを作り、役割分担をして暮らす社会性生物です。アリの社会には、解明されていない、たくさんの不思議があります。私はそんなアリたちが、好きで好きでしかたありません」遥が続ける。
「私は今まで、マーケティングについて勉強をしてきました。でも、それがビジネスの現場で、実際にどのように活かされているのかを知りません。それが知りたくて、勇気を出してこの世界にやってまいりました。ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、一生懸命に頑張りますので、どうぞよろしくお願いします!」
みんなが拍手をした。
「いやいや小橋さん、『この世界にやってきました』って、あなた天使ですか?」奥山が笑う。
「たしかに小橋さんは、どこか別の世界からいらっしゃったような、少し神秘的な佇まいですよね」
鮎川が言う。そんなことを真顔で言う鮎川もおかしくて、みんなが笑った。遥は恥ずかしそうに頬を染めながら、笑顔で首を大きく振って否定した。
「こばし、って言うと、どうも、うちの古狸が思い浮かんで、いけねえなあ」古狸とは総務部長の古橋のことだ。古橋はタヌキの置物によく似ている。
「俺らは、遥さんって呼ばせてもらうのはどうだろう?」
源次郎がみんなに提案した。
「はい!ぜひ!」遥はこたえた。
メンバーが拍手して、遥はうれしそうにお辞儀をする。