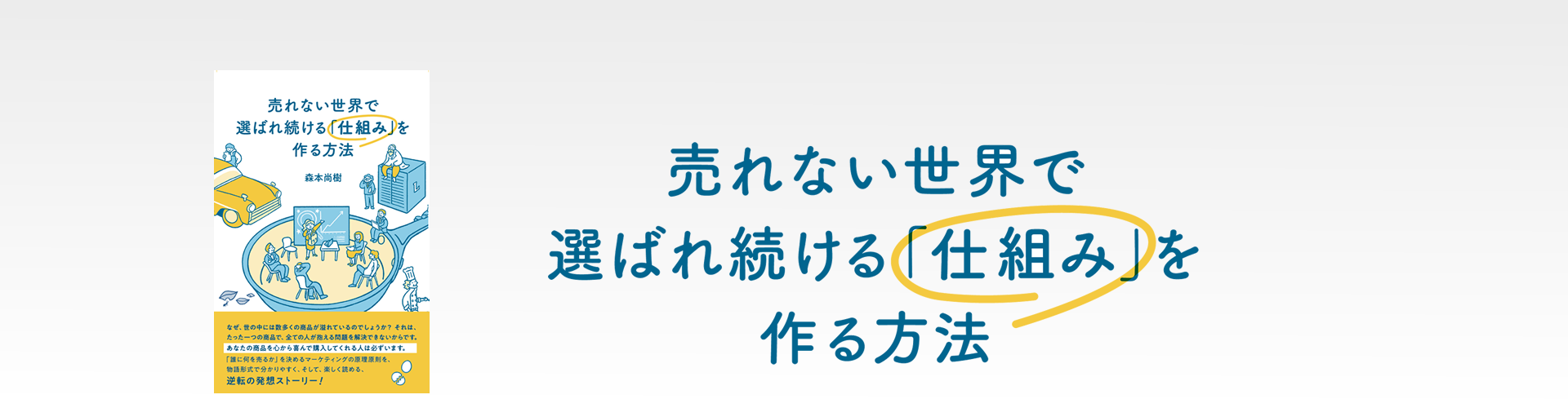
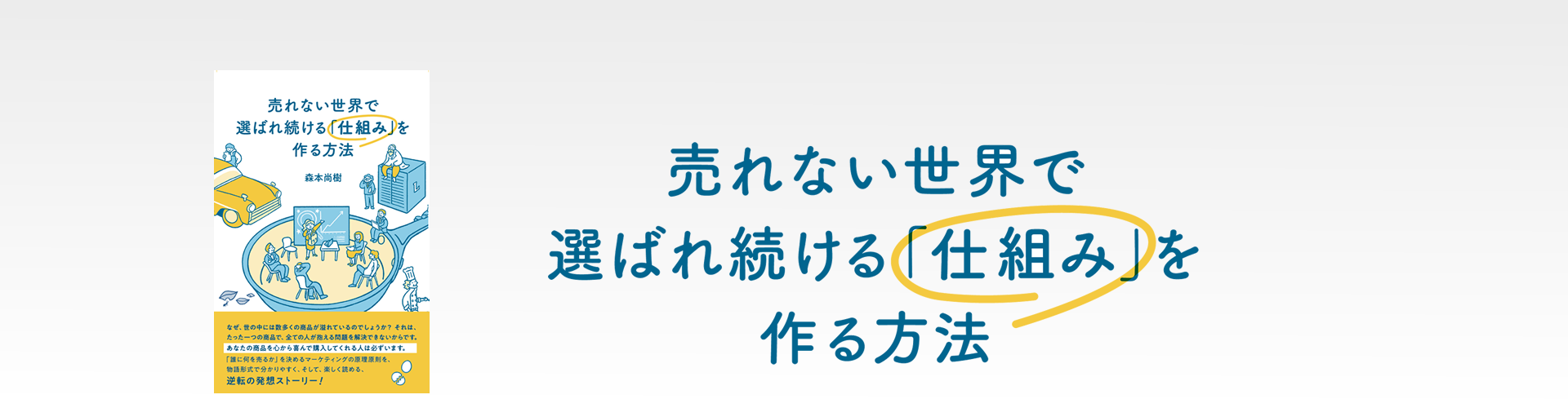
遥が学んだマーケティング理論
設計図が足りない!
さあハルカ、講義を始めよう。
最初の講義は、マーケティングの設計図「マーケティングピラミッド」についてだ。
ビジネスパーソンの多くは、マーケティングを正しく理解できていない。学べば学ぶほど、マーケティングは複雑で、難解で、覚えることが多すぎると感じて挫折してしまう。
なぜか?
マーケティングには、たくさんの理論がある。幾人もの偉大な先人たちが、数多くの理論を提唱してきた。現代にあっても、新たなノウハウが誕生しては消えている。これらを無秩序に学んでしまうことで、人々はマーケティングを複雑で、難解で、覚えることが多すぎると誤認してしまう。
これは設計図を見ずに、何かを組み立てようとすることに似ている。
いかに偉大な先人が残したマーケティング理論であったとしても、それはマーケティング全体から見れば、ひとつのパーツに過ぎない。マーケティングは、いくつものパーツでできているのだ。
では、どうすればマーケティングを理解できるようになるのか?答えは簡単だ。
マーケティングの設計図を携えることだ。設計図さえあれば、マーケティングを正しく理解し、骨太なマーケティングプランを組み立てることができるようになる。
さて、設計図について学ぶ前に、まず、私たちはその設計図を用いて、何を完成させようとしているのかを知らなくてはならない。完成像がイメージできなければ、いかなるものも、うまく組み立てることはできない。
私たちが作ろうとしているもの、それは「顧客から選ばれ続ける仕組み」である。これこそがビジネスにおけるマーケティングの完成像だ。
覚えておいてほしいのは、選ばれることではなく、「選ばれ続けること」がめざすべきゴールだということだ。さらに言えば、その仕組みを作ることが真のゴールだということだ。
マーケティングとは「顧客から選ばれ続ける仕組みを作ること」。このように定義して覚えておくと実践で役に立つ。
さて本題に入ろう。
マーケティングの設計図はピラミッドの形をしている。これがマーケティングピラミッドだ。
ピラミッドはその頂点から
1.戦略
2.作戦
3.戦術
の順に多層化されている。それぞれのモジュールには明確な目的がある。
1.戦略
戦略を考える目的は「商品の差別化ポイントを作る」ことである。差別化することで顧客は確信を持って商品が選べるようになる。
2.作戦
作戦を立てる目的は「顧客の購入障壁を撤廃する」ことである。そうすることで、顧客は購買へのスタートラインに立てる。
3.戦術
戦術を動かす目的は「認知の拡大」である。そもそも顧客に商品の存在を知ってもらわなければ何も始まらない。
こうして考えると、戦略・作戦・戦術のいずれもが、顧客から選ばれ続ける仕組みを完成させるためには必要不可欠な要素だということが分かるはずだ。
マーケティングピラミッドの各要素を簡単に説明しておこう。
最上位に位置するのは戦略である。ここがマーケティングの心臓部だ。戦略は、その中でさらに3つの階層構造になっている。上位から順に
①大戦略
②競争戦略
③差別化戦略
である。
マーケティングピラミッドの、上位に位置する要素ほど、上位の概念である。つまり、大戦略が最上位の概念だということになる。
①大戦略
(1)ターゲット(誰に)
(2)コンセプト(何を売るのか?)
大戦略はターゲットとコンセプトを決めることだ。言い換えると「誰に何を売るのか?」を決めることと理解すればいい。誰に何を売るのか?について、マーケティングでは完璧な答えがある。それは「困っている人に問題解決手段を売る」という答えだ。何も困ってもいない人に、何だかよく分からない商品やサービスを売るくらい大変なことはない。
②競争戦略
(3)ライバルの弱みを突く
(4)自社の強みを活かす
競争戦略は簡単に言えば、ライバルの弱みを突き、自社の強みを活かすことに尽きる。ライバルとの差が明確でなければ、顧客は購入すべき商品を、確信を持って選べなくなる。
③差別化戦略
(5)商品を差別化する
差別化戦略は商品そのものの差別化を試みることである。差別化は難しいと感じるかもしれないが、今ある商品の機能や性能、特徴や利点を捨てて、正反対に置き換えれば、実は容易に発想できる。
次の階層は作戦である。作戦の中には、
④価格戦略
⑤流通戦略
⑥販売戦略
3つのファクターが並列に並ん
簡単に言えば「いくらで売るか」「どこで売るか?」「どのようなプロセスで売るか?」ということだ。
この問いにも答えがある。それは、「顧客が買いやすい価格を設定して」「顧客が買いやすい場所で」「顧客が買いやすいプロセスで販売する」という鉄壁の答えだ。
そう、作戦の目的は、顧客の購入障壁の撤廃である。
最後の戦術はピラミッドの最下層にある。その目的は認知の拡大である。
戦術の実行手順は次の2ステップだ。
⑦戦略と作戦で決めたことの言語化
⑧媒体の選択と発信
ちなみに、媒体は以下のようなものが考えられる。ホームページ、ランディングページ、オウンドメディア、メールマガジン、ダイレクトメール、雑誌広告、インターネット広告、カタログ、チラシ、ソーシャルネットワーキングサービス、看板、パブリックリレーションズなどだ。営業活動や代理店政策なども、人を媒介した認知の拡大策だと考えれば、媒体にカテゴライズできる。
戦術を実行する上で忘れてはいけないのは、「戦略の失敗は戦術では補えない」という原理原則である。戦術を動かす前に、戦略と作戦を明確化しなくてはならないということだ。
マーケティング戦略が正しくないと、営業活動はもちろん、ホームページやチラシなどの戦術面をいくら強化しても成果は出せない。また、マーケティングの実質的なリスクは、ほぼ戦術に集中する。つまり、戦略なき戦術は破滅を招くということだ。これは声を大にして伝えたい。
以上がマーケティングの設計図、マーケティングピラミッドの全体像だ。この中に含まれていない、マーケティングリサーチなどは、全体に関係している理論だと理解すればいい。例えば、ライバルの弱点を発見するためのリサーチもあれば、市場価格を調べるためのリサーチもある。広告効果を測定するリサーチも重要だ。それぞれが戦略、作戦、戦術を確定させるためのリサーチだったと気づくだろう。
これからマーケティングを学ぶ時は、まずマーケティングピラミッドのどの部分について論じられた理論なのかを確認しなさい。そうすれば理解は数倍速く、そして、数段深くなるだろう。
6
遥は黒板にマーケティングの設計図であるマーケティングピラミッドを書き、すべてのモジュールとファクターを書き入れた。
「僕らが学んだことも、実はこのマーケティングピラミッドの中に含まれるということなんですよね」岡田が遥に尋ねる。
「はい。例えば市場からの反応を獲得するために組み合わせるべき四つのP、4Pのプロダクトは戦略の中の③差別化戦略。プライスは作戦の中の④価格戦略。プレイスは同じく作戦の中の⑤流通戦略。プロモーションも作戦の中の⑥販売戦略と、.戦術に分類することができます」遥がこたえる。
「3Cは?」鮎川が聞く。
「3Cはマーケティングの登場人物を示します。この三つのCはいずれも戦略の中に含まれます。カスタマーは①大戦略、コンペティターは②競争戦略、カンパニーも同じく②競争戦略に含まれます」
遥は黒板に次々に古典のマーケティング理論との相関を書き込んでいく。
「遥さんに整理してもらうと、俺らが学んできたことが、どんどんと腑に落ちてくな」源次郎は黒板を前に感動の面持ちだ。
「セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングの頭文字である、STPは、市場を細分化して、そのどの市場をターゲットにするかを決め、自分たちの立ち位置を顧客に対して明確にするためのフレームワークです」遥がこたえる。
「あ!もしかしてSTPは大戦略、つまり、誰に何を売るのか?を決定する手順ではないですか?」
奥山が黒板に近づきピラミッドの①大戦略を指差しながら、遥のほうを振り返る。
「はい。私も奥山さんと同じ意見です。STPは実践でも極めて有効なフレームだと言われています」
奥山は遥に同じ意見だと言われたのがよほどうれしかったのか、ウルウルとした目で遥を見ている。遥は続ける。
「4P、3C、STPなどの基礎理論は、決して初心者向きの理論などではありません。プロのマーケターでも、常にそこに回帰するマーケティングの核となる重要理論です」
「僕たちマーケティング室の使命は、片山鋳造のマーケティングピラミッドを完成させ、お客さまから選ばれ続ける仕組みを作ることだったんですね」